自宅の住所を使って登記するのは嫌だから、バーチャルオフィスの住所を借りたいと考えている方少なくないと思います。
しかし、バーチャルオフィスでの登記って法律的に大丈夫なのか気になるところだと思います。
そこで今回はそんな方のために、バーチャルオフィスで登記する際の違法性などについてどこよりもわかりやすく紹介していきたいと思います。
この記事を最後まで読むことで以下の3点について理解することができます。
- バーチャルオフィスでの登記の可否
- バーチャルオフィスで登記が禁止されている業種
- バーチャルオフィスで登記するデメリット
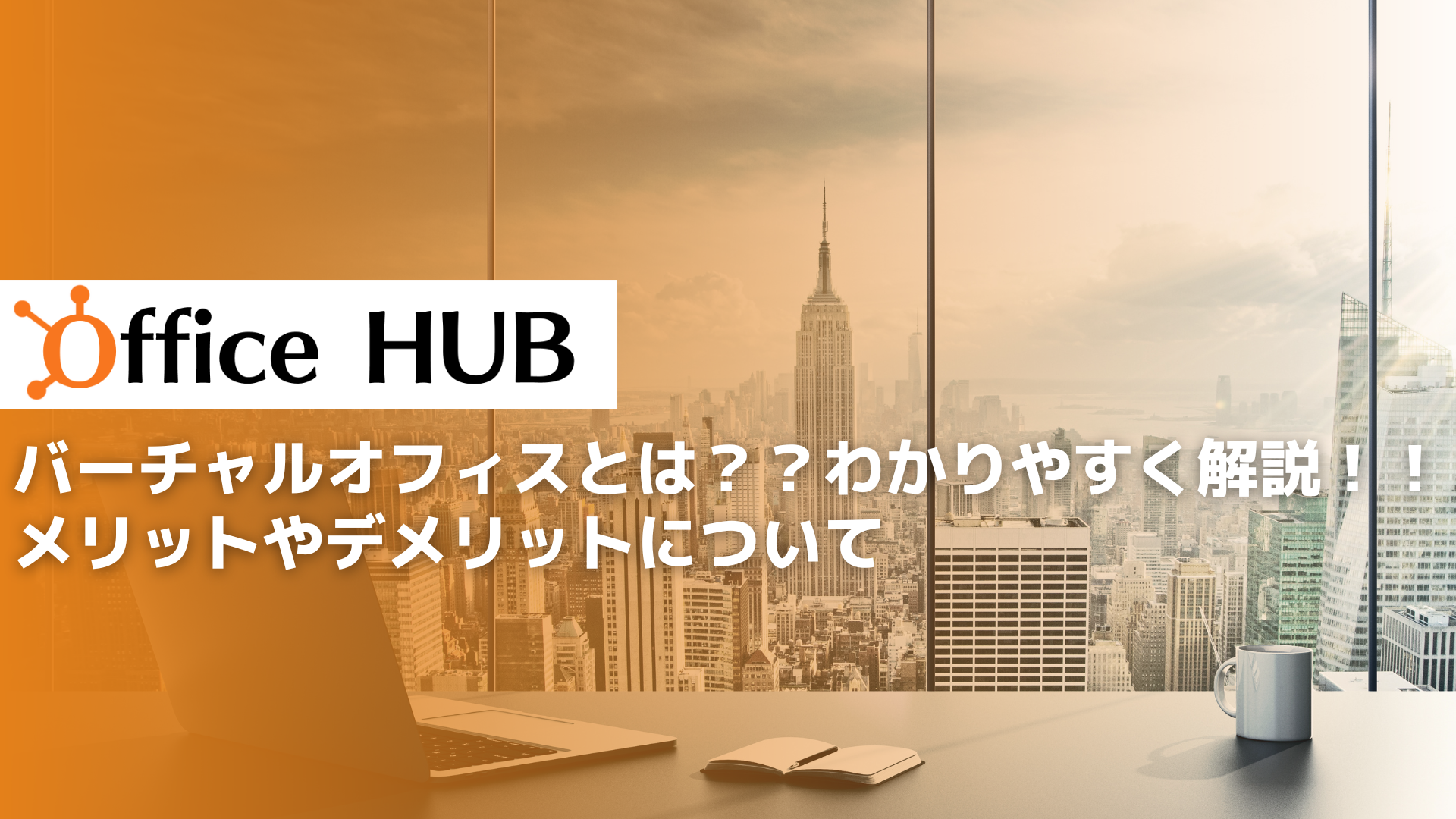
「バーチャルオフィスってなに??」 「バーチャルオフィスを利用すると何がいいの??」 起業を考えている方やネットショップの運営している人は、よく「バーチャルオフィス」というサービスについて耳にすることがあるでしょう。 ですが、一体何なのかよくわかっていない方も多いと思います。 そこで今回は、...
「バーチャルオフィスってなに??」 「バーチャルオフィスを利用すると何がいいの??」 起業を考えている方やネットショップの運営している人は、よく「バーチャルオフィス」というサービスについて耳にすることがあるでしょう。 ですが、一体何なのかよくわかっていない方も多いと思います。 そこで今回は、...
バーチャルオフィスで登記するのは違法ではないの??
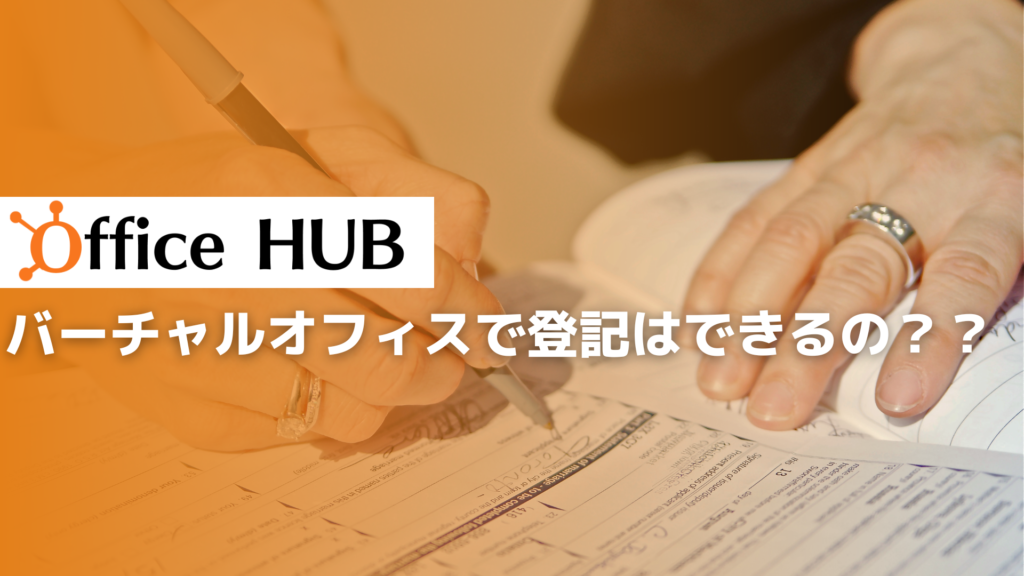
バーチャルオフィスで登記すること自体は、違法ではありません。
しかし、刑法第157条1項が適用されるため違法だと主張している人が少数いるため、違法という論がネットで流れています。
その違法だと諭す内容は、「会社法第27条3号にて会社の成立・存続に際して『本店所在地』を定めることが求められている」というものです。
この「本店所在地」は、実際に営業実態がない住所は当てはまらず、バーチャルオフィスは営業実態がないとされていました。
そのため、「本店所在地」のない住所を提供するバーチャルオフィスで法人登記することは『公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条1項)』になるため、違法だという論となります。
以上の内容から、バーチャルオフィスに営業実態があるかがカギとなります。
しかし、バーチャルオフィスは届いた荷物が会員に届けられたり、バーチャルオフィスに来客が来ても、会員に連絡がいくため営業実態には問題がないという反論があります。
どちらの論に賛同するかは、各々の自由ですが現在は、バーチャルオフィスには営業実態があるという論が世の中的には通っており、現時点で違法にはなりません。
そもそも違法性があったら芸能人を広告に起用したり、企業が利用したりしないからそこは安心して大丈夫!!
バーチャルオフィスで登記はできるの??
バーチャルオフィスで拠点の住所や、その他サービスを利用して登記をすることは可能です。
本来、起業を行う際には、どの場所を拠点として事業を行うのか示すために法人登記が必要です。
その登録をするための方法として、テナントを借りて拠点にしたり、自宅を拠点にするなどして住所を作らなければなりません。
ただし、テナントを借りる方法だと時間やコストが多く掛かってしまったり、自宅の住所を利用するとプライベート情報が流出してしまうなど、問題点が多くありました。
そのため、バーチャルオフィスで受けられる住所貸しのサービスは、プライバシー保護の観点や早急に企業を行いたい人、コストをできるだけ抑えたい人からするとすごく便利なサービスです。
法律上もバーチャルオフィス自体に問題はないため安心です。
しかし、一部例外の事業や利用方法もあるので次章でご紹介します。
格安で住所を利用できるのはありがたい!!
バーチャルオフィスで登記できない業種
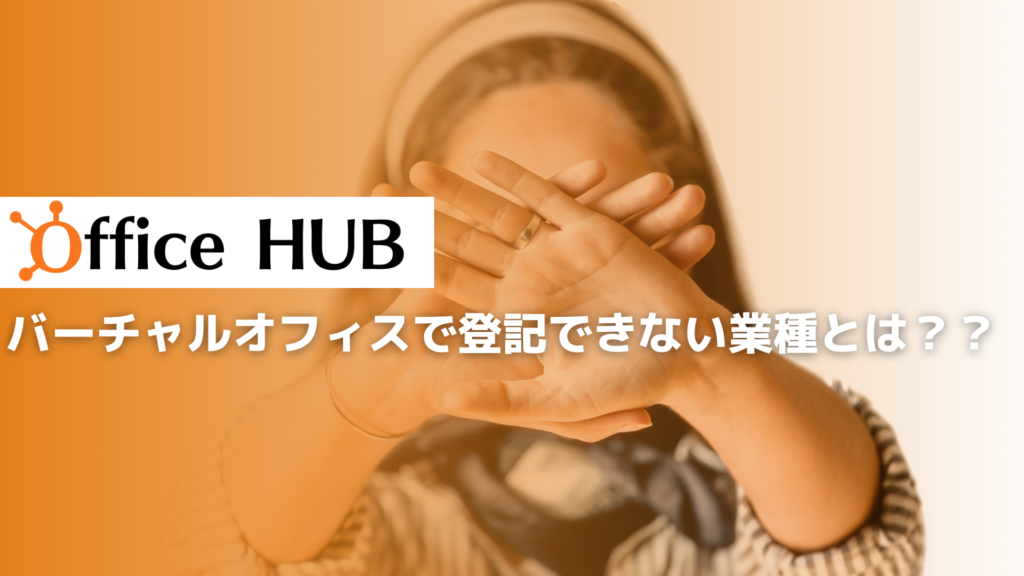
違法ではありませんが、バーチャルオフィスで登記できない業種がいくつかあります。
代表的な業種としては以下となります。
登記できない業種
- 人材派遣業
- 不動産業
- 士業
- 探偵業
- 建設業
- 不用品回収業
- 金融商品取引業
- 風俗業
人材派遣業
人材派遣会社は、バーチャルオフィスで登記できないとされています。
人材派遣業には、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業の2種類に分けることができ、結論、どちらの派遣業でもバーチャルオフィスでの起業は難しいです。
まず、一般労働者派遣業とは、登録型や臨時雇用型など、正社員として雇われていない人がアルバイトの扱いで派遣を行うことを指します。
人材派遣会社の起業を行う際に20平方メートル以上の事業所が必要で、この拠点に事務所を構えているという賃貸借契約書の提出も必須です。
バーチャルオフィスの場合、賃貸借契約書は発行されず、契約を結ぶ扱いにならないため許可が下りません。
次に、特定労働者派遣業は、派遣会社に常用雇用されている人が派遣提携している他社で継続して業務を行うことを指します。
特定労働者派遣業の場合、一般労働者派遣業のように書類の提出は必要ありませんが、バーチャルオフィスであることがバレると会社運用の許可を取り消されることもあります。
不動産業
不動産業は、バーチャルオフィスで登記ができないとされています。
そもそも、不動産業を行うためには宅建の免許を取得することが必要で、免許取得をした上で都道府県の役所に、申請を出す必要があります。
その際の申請には、独立した事務所が必要とされており、その事務所内で個別にお客さんと話せるスペースや接客用の備品が揃っているかも確認されます。
バーチャルオフィスは住所を簡単に借りることができますが、不動産業のように厳しいチェックがある場合、登記は認められません。
士業
士業である、税理士、司法書士、弁護士等の業種は、バーチャルオフィスで登記できないとされています。
これらの士業には、それぞれ管轄の税理士会や司法書士会、弁護士会などで申請を行い事業を行うための登録が必要となります。
その場合、独立した事務所を用意する必要があり、会社の住所も提出することになります。
詳細は、それぞれの士会によって異なりますが例えば、弁護士の場合、独立した相談スペースが必要であるため共有建物では登録ができません。
個人情報を守るためにも、共有部の事務所の士業は不可となり、バーチャルオフィスの住所では起業が行えません。
探偵業
探偵業は、バーチャルオフィスでの登記ができないとされています。
探偵の仕事を行うには、警察への届け出が必要です。
届け出をして、公安委員会から「探偵業届出免許証」の交付を受ける必要があり、構えた事務所の誰からも目につきやすい場所に免許証の掲示が常に必須となります。
この証明書は、探偵業がプライバシーにかかわる重要な情報を扱うことから、行政が管理するために発行しているもので、届け出がされていない探偵業の運営は違法となります。
そのため、免許証が掲示されていない場所で、相談者は探偵に依頼することができません。
その証明をバーチャルオフィスに掲示することはできませんし、作業場がないバーチャルオフィスでは拠点で相談が受けられないため、このような共有事務所での業務は不可となります。
建設業
建設業は、バーチャルオフィスでの法人登記ができないとされています。
建設業も運営するためにも、許可が必要な業種です。
許可を取るための審査の段階で、「請負契約の見積や入札、契約締結などができる実体的な行為ができる事務所」が必要になり、その場所で法人登記をすることとなります。
そのため、法人登記ができるのは実際に作業ができる事務所となるので、作業ができない住所を借りるだけのバーチャルオフィスでは、残念ながら法人登記ができません。
不用品回収業
不用品回収業は、バーチャルオフィスの法人登記ができないとされています。
不用品回収業は、産業廃棄物の処理を行う業務となり、産業廃棄物を扱う場合、都道府県や政令指定都市に取り扱いの許可を取る必要があります。
また、産業廃棄物を取り扱う人のことを、産廃業者と言い、産廃業者として認められるためには、相応の施設や設備、その人に処理を行う能力があるかが見られます。
更に、継続的に的確な事業を行えることも許可が下りる重要な項目の1つです。
それらのことを総合的に考えた時、バーチャルオフィスの住所では基準を満たされず許可が下りないでしょう。
金融商品取引業
金融商品取引業を行う際は、バーチャルオフィスでの登記ができないとされています。
金融商品取引法は、人の大事な資産を扱うため財務局で金融商品取引業者の登録をする必要があります。
金曜商品取引業は投資家や監督官庁など問い合わせや照会に、速やかな対応が求められることが多く、その対応ができるかの環境も見定められ要求されます。
また、登録を行うためには、営業を行う場所に標識という事務所の図面や職員の配置図を表示するものが必要で、その標識を掲示する予定の場所を申告する必要があります。
更に、財務局の審査内容によっては拠点の賃貸借契約書コピーを審査書類として渡す必要もあり、バーチャルオフィスでの住所登記を前提にはしていません。
そのため、バーチャルオフィスの住所で申請をした場合、財務局の許可はおりません。
風俗業
風俗業をする場合、バーチャルオフィスの住所では法人登記ができないとされています。
風俗営業を行う場合は、警察に申請をだし公安委員会の許可を得る必要があります。
その理由は、風俗業が適正に行われるよう公安委員会が監視を継続していくための制度を適用するためです。
その申請には、もちろん拠点としての事務所が必要で、更に公安委員会の見回りがあった際に対応できる従業員が必要です。
適正に運営しているかという判断をするためにも、営業をする場所はバーチャルオフィスの住所では登録ができません。
バーチャルオフィスで登記する際のメリット
バーチャルオフィスで登記することで以下のメリットがあります。
- 初期費用を削減できる
- プライバシーを守れる
- 信頼性が向上する
初期費用を削減できる
バーチャルオフィスを利用すると、初期費用を大幅に削減できます。
物理的なオフィスを借りると、家賃や敷金、礼金、内装工事などの高額な費用がかかります。
しかし、バーチャルオフィスではこれらの費用が不要です。
例えば、通常のオフィスを借りる場合、数ヶ月分の家賃や内装工事に数百万円がかかることがあります。
バーチャルオフィスなら月額料金のみで済み、初期費用を大幅に抑えることができます。
プライバシーを守れる
バーチャルオフィスを利用することで、プライバシーを守ることができます。
自宅住所を登記しなくて済むため、個人情報を公開せずに事業を行うことができます。
例えば、オンラインショップを運営する際に、特定商取引法に基づいて住所を公開する必要があります。
バーチャルオフィスの住所を利用することで、自宅の住所を公開せずに済むため、プライバシーが保護されます。
信頼性が向上する
バーチャルオフィスを利用することで、会社の信頼性を向上させることができます。
都心の一等地の住所を登記に使用することで、会社のイメージが良くなり、取引先や顧客からの信頼を得やすくなります。
例えば、創業間もない企業が一等地の住所を登記に使用することで、高級感や信頼性をアピールできます。
これにより、取引先や顧客からの信用度が向上し、ビジネスチャンスが広がります。
バーチャルオフィスで登記する際のデメリット
バーチャルオフィスで登記をする際にデメリットとして以下の3つが挙げられます。
- 法人登記ができない業種がある
- 法人口座が開設出来ない場合がある
- 住所は他の会員も利用している
法人登記ができない業種がある
先ほどご紹介したように業種によって法人登記ができない場合があるので注意が必要です。
法人登記ができない業種は、営業をするために管轄機関の許可が必要なものがほとんどです。
例えば、営業に伴い個人情報を取り扱う対応が必要な業種は、個別に仕切られた相談ブースが必要だったり、専門的な知識が必要な業種は許可書の掲示が必要になります。
逆に管轄機関の許可が必要ない業種は基本的に法人登記ができると考えても良さそうです。
ただし、業界によって詳細の条件がある場合も考えられるので、相談窓口で確認をしてから法人登記の手続きをしましょう。
法人口座が開設出来ない場合がある
バーチャルオフィスによっては、法人登記ができても法人口座の開設ができない場合があります。
前提として、バーチャルオフィスの住所で法人登記をする場合も法人口座の開設は可能です。
しかし、バーチャルオフィスによっては、過去にトラブルを起こしている住所がそのまま適用されていることもあり、審査落ちや開設までに時間が掛かる可能性もあります。
また、バーチャルオフィスは金融機関側からすれば実体のない住所と判断されてしまうこともあり、うまく審査が進みません。
審査が通過しやすいように、事業内容のわかる資料を用意したり稼働が増えることも想定しておいてください。
更に、口座開設以外にも信用性が薄いと判断されてしまえば、金融機関からの融資が難しくなります。
将来的に大規模な事業を考えており、融資も必要であれば法人登記する住所は信頼性の高いバーチャルオフィスから選ぶことをオススメします。
住所は他の会員も利用している
バーチャルオフィスで借りる住所は、その拠点の会員全ての人が同じものを利用しています。
法人登記するために借りる住所は、もちろんホームページや各種名刺など会社概要として公開している企業がほとんどです。
そのため、ホームページで住所を検索すれば同じ住所を利用している会社が複数出てきます。
また、調べ方によってはバーチャルオフィスであることが顧客にバレます。
バーチャルオフィスで法人登記をすること自体、悪いことではありませんが、業種によってはオフィスを持たないことが不利に働くこともあるので注意が必要です。
登記ができるオススメのバーチャルオフィス5選!!
法人登記ができるオススメのバーチャルオフィスを5つご紹介します。
GMOオフィスサポート
 GMOオフィスサポートは、GMOインターネットグループ株式会社が運営しています。
GMOオフィスサポートは、GMOインターネットグループ株式会社が運営しています。
法人登記ができるプランは月額1,650円から利用できます。
このサービスの特徴は、都心の一等地にあるオフィスを低価格で利用できることです。
郵便物の転送やLINEでの通知、ウェブからの転送依頼が可能で、便利です。
また、ビジネス支援サービスも充実しており、特に起業家やスタートアップに向いています。

2021年の12月に利用開始したGMOオフィスサポートですが、どのようなサービスが受けれて、実際に利用した方の感想など気になりますよね。そこで今回は、GMOオフィスサポートのサービス内容や評判、どのようにして利用するのかなどについて紹介していきたいと思います。この記事を最後まで読むこ...
2021年の12月に利用開始したGMOオフィスサポートですが、どのようなサービスが受けれて、実際に利用した方の感想など気になりますよね。そこで今回は、GMOオフィスサポートのサービス内容や評判、どのようにして利用するのかなどについて紹介していきたいと思います。この記事を最後まで読むこ...
GMOグループが運営
DMMバーチャルオフィス

DMM バーチャルオフィス![]() は、合同会社DMM.comが運営しています。
は、合同会社DMM.comが運営しています。
法人登記ができるプランは月額1,650円からで、ビジネスプランは月額2,530円から提供されており、郵便物転送などのサービスも含まれています。
このサービスの特徴として、都心の一等地にオフィスがあり、銀座や渋谷などの主要エリアに拠点を持つことでビジネスの信頼性やブランド力を高めることができます。
さらに、スマートフォンを使って郵便物の管理や通知を受け取ることができ、利便性が非常に高いです。
また、郵便物転送や貸し会議室、来客対応、電話秘書代行など、多彩なオプションサービスを提供しており、利用者のビジネスニーズに柔軟に対応しています。

「DMMバーチャルオフィスは利用しても大丈夫なの??」 「DMMバーチャルオフィスってどんなサービスが使えるの??」 大手DMMが運営するDMMバーチャルオフィスですが、どんなサービスが利用できるのか気になりますよね。 また、本当に利用しても後々問題ないのかなど、今利用を検討されている方は不安も少し...
「DMMバーチャルオフィスは利用しても大丈夫なの??」 「DMMバーチャルオフィスってどんなサービスが使えるの??」 大手DMMが運営するDMMバーチャルオフィスですが、どんなサービスが利用できるのか気になりますよね。 また、本当に利用しても後々問題ないのかなど、今利用を検討されている方は不安も少し...
DMMグループが運営
レゾナンス

レゾナンス![]() は、東京と横浜を中心に展開しているバーチャルオフィスサービスで、運営しているのはレゾナンス株式会社です。
は、東京と横浜を中心に展開しているバーチャルオフィスサービスで、運営しているのはレゾナンス株式会社です。
このサービスは、法人登記が月額990円からできるという業界でも非常にリーズナブルなプランを提供しています。
レゾナンスの大きな特徴は、便利で多機能なオプションが充実している点です。
例えば、スマートフォンで会社設立の手続きを完了できる「スマホde会社設立」サービスや、郵便物の写真通知、電話秘書代行サービスなどがあります。
また、会員限定で法人口座の開設支援や法人クレジットカードの紹介も行っています。
これらのサービスを利用することで、起業時の負担を大幅に軽減することができます。
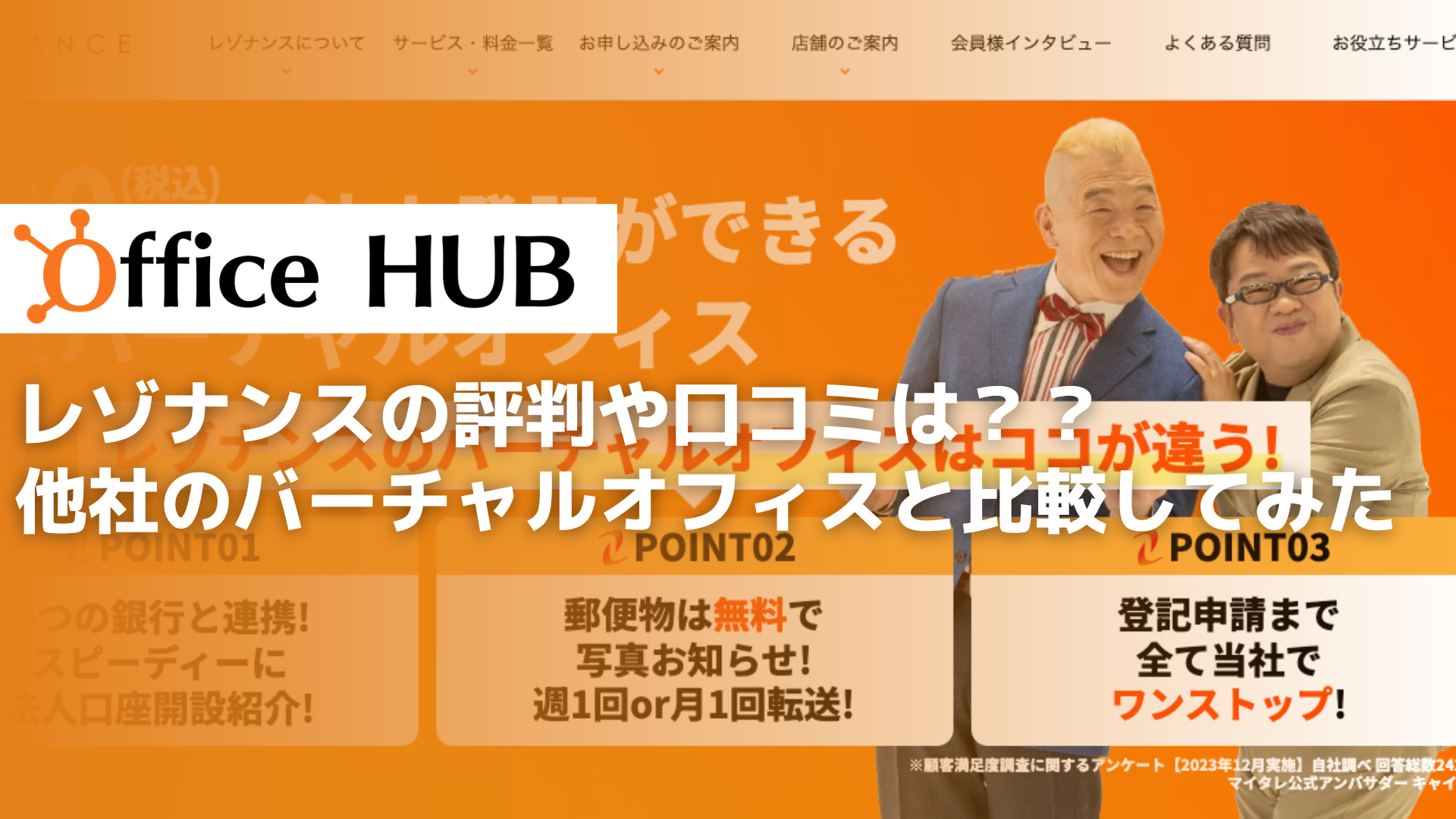
「レゾナンスってどんなバーチャルオフィスなんだろう...」 バーチャルオフィスの中でも評判の良いレゾナンスですが、実際にどんなサービスなのか気になりますよね。 そこで今回は、レゾナンスのサービス内容やプラン、評判などについてどこよりも詳しく紹介していきたいと思います。 この記事を最後まで読むこ...
「レゾナンスってどんなバーチャルオフィスなんだろう...」 バーチャルオフィスの中でも評判の良いレゾナンスですが、実際にどんなサービスなのか気になりますよね。 そこで今回は、レゾナンスのサービス内容やプラン、評判などについてどこよりも詳しく紹介していきたいと思います。 この記事を最後まで読むこ...
今なら3ヶ月無料!!
NAWABARI
 NAWABARI
NAWABARI![]() は株式会社Lucciが運営しているバーチャルオフィスサービスです。
は株式会社Lucciが運営しているバーチャルオフィスサービスです。
このサービスでは、法人登記が月額1,100円から可能です。
また、ネットショップ運営者に特化したプランがあり、月額1,100円で利用できるため、特にコストを抑えたい人にとって魅力的です。
さらに、郵便物の転送サービスや電話対応サービスが含まれており、これらを利用することで、オフィスを持たずにビジネスを運営することができます。
NAWABARIは、セキュリティ対策として荷物のGPS追跡や盗聴器探知機の使用なども行っており、安心して利用できる環境が整っています。
また、法人銀行口座の開設支援や法人クレジットカードの紹介も行っており、ビジネスの立ち上げや運営に必要なサポートが充実しています。
初期費用無料!!
バーチャルオフィス1

バーチャルオフィス1![]() は、株式会社バーチャルオフィスワンが運営しています。
は、株式会社バーチャルオフィスワンが運営しています。
このサービスは東京都渋谷区と広島市に拠点を持ち、法人登記が月額880円で可能です。
初期費用として5,500円が必要ですが、このプランには月4回の郵便転送も含まれています。
バーチャルオフィス1の特徴として、非常にリーズナブルな料金設定と便利なサービスが挙げられます。
例えば、郵便物の転送サービスや電話転送サービス、さらには司法書士や税理士の紹介など、起業や事業運営に役立つ多様なサービスを提供しています。
また、会議室の利用も可能で、必要に応じて直接対面での打ち合わせも行えます。
ワンプランだけ!!
>

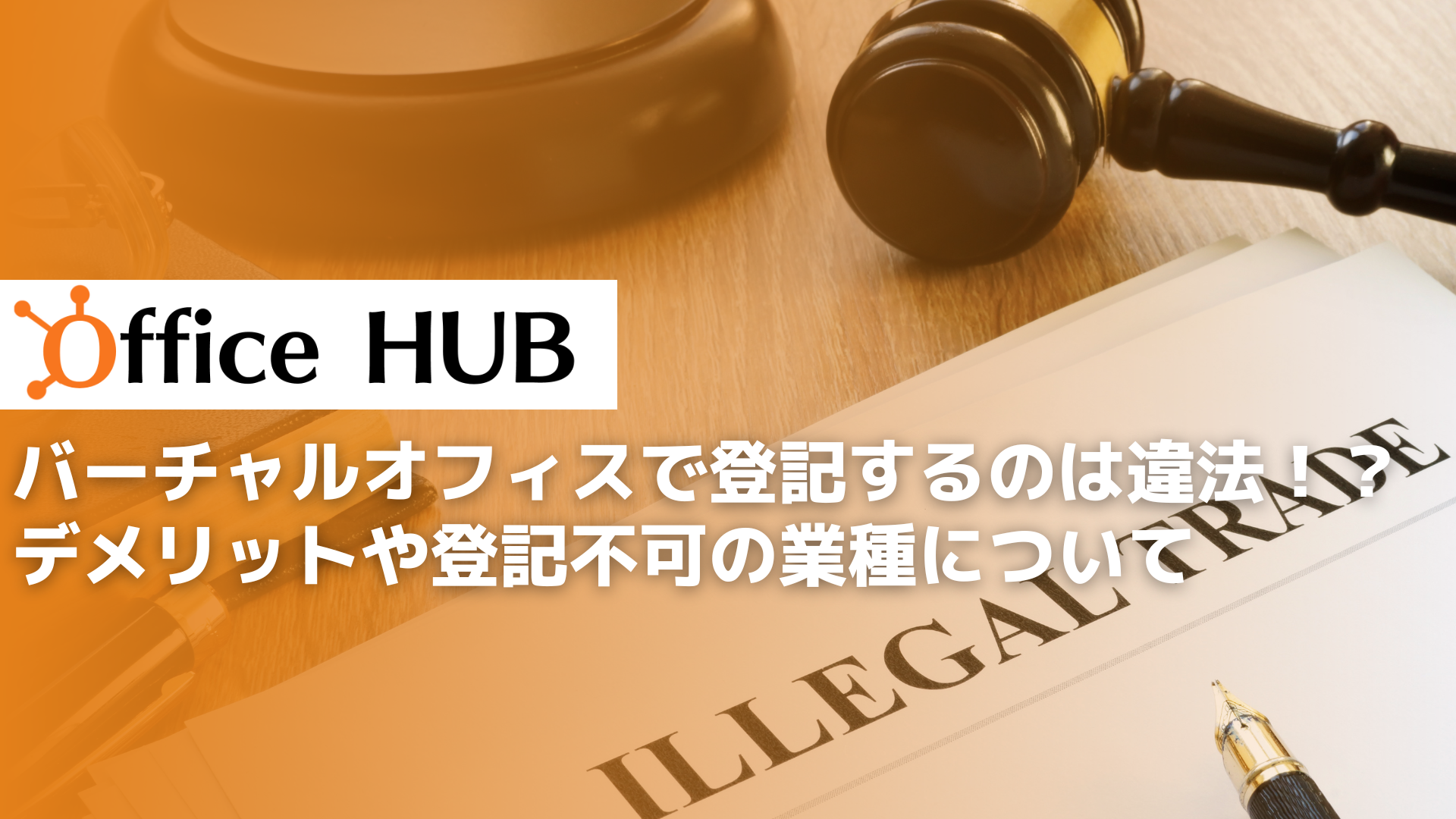

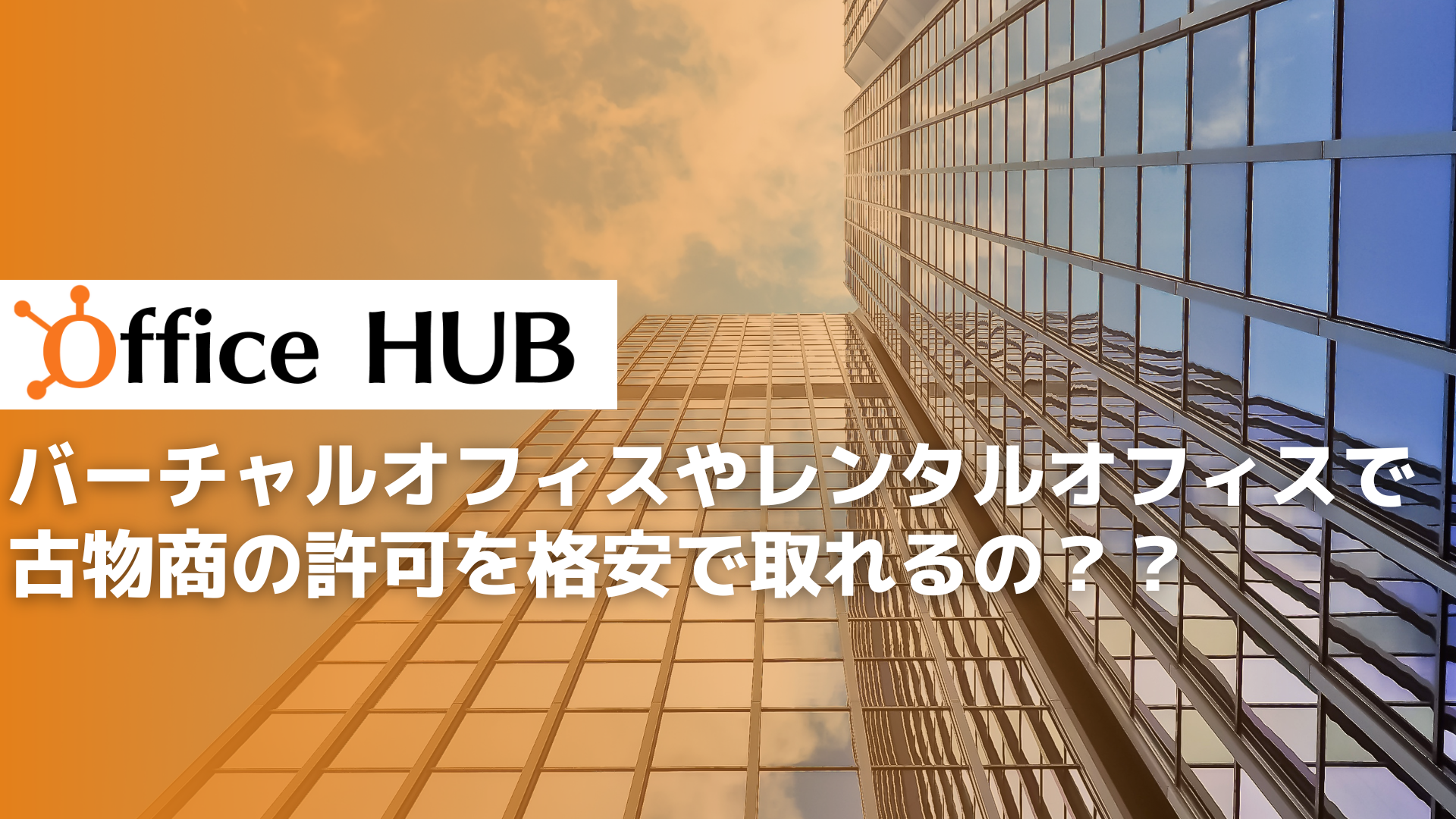
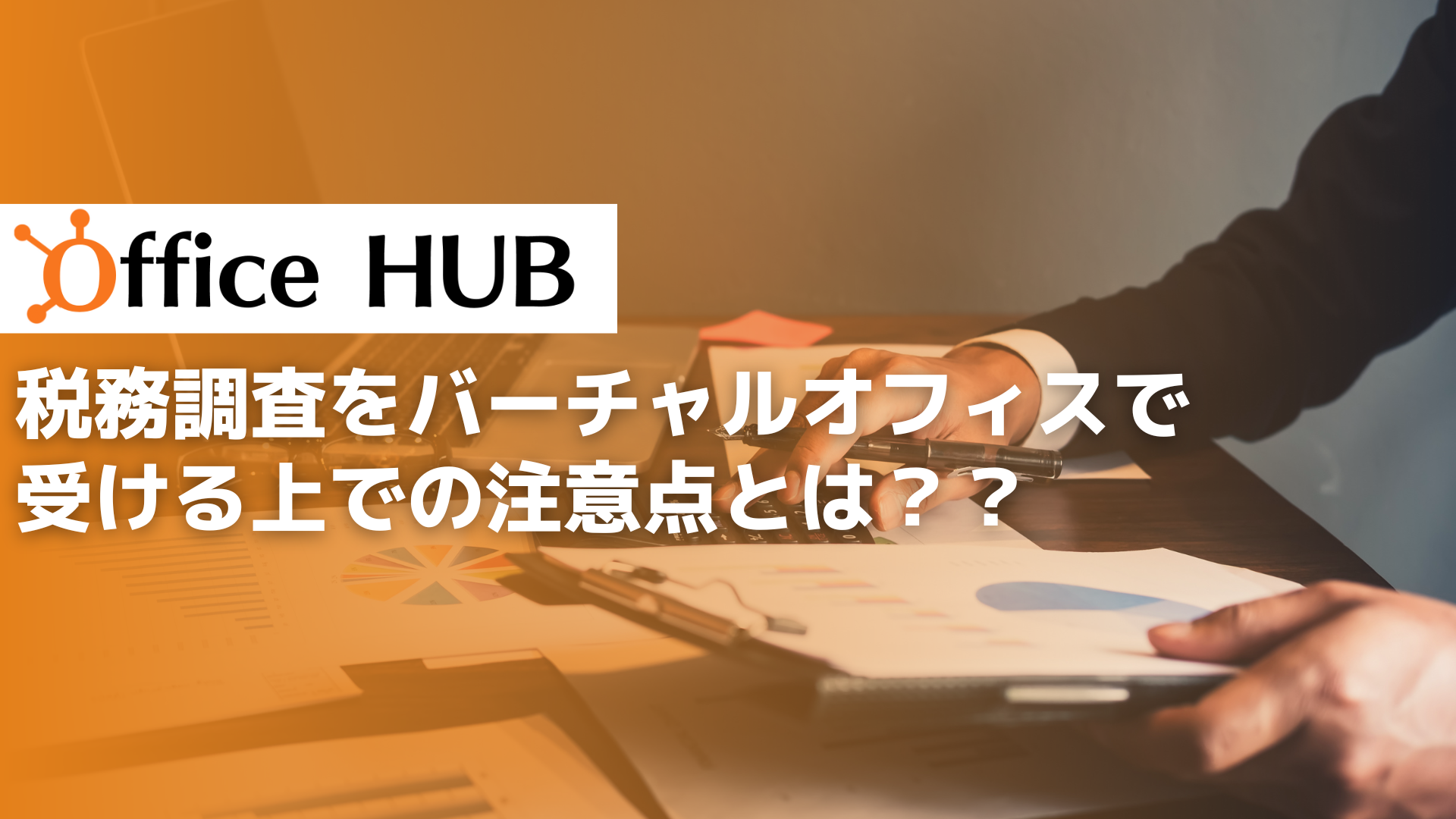
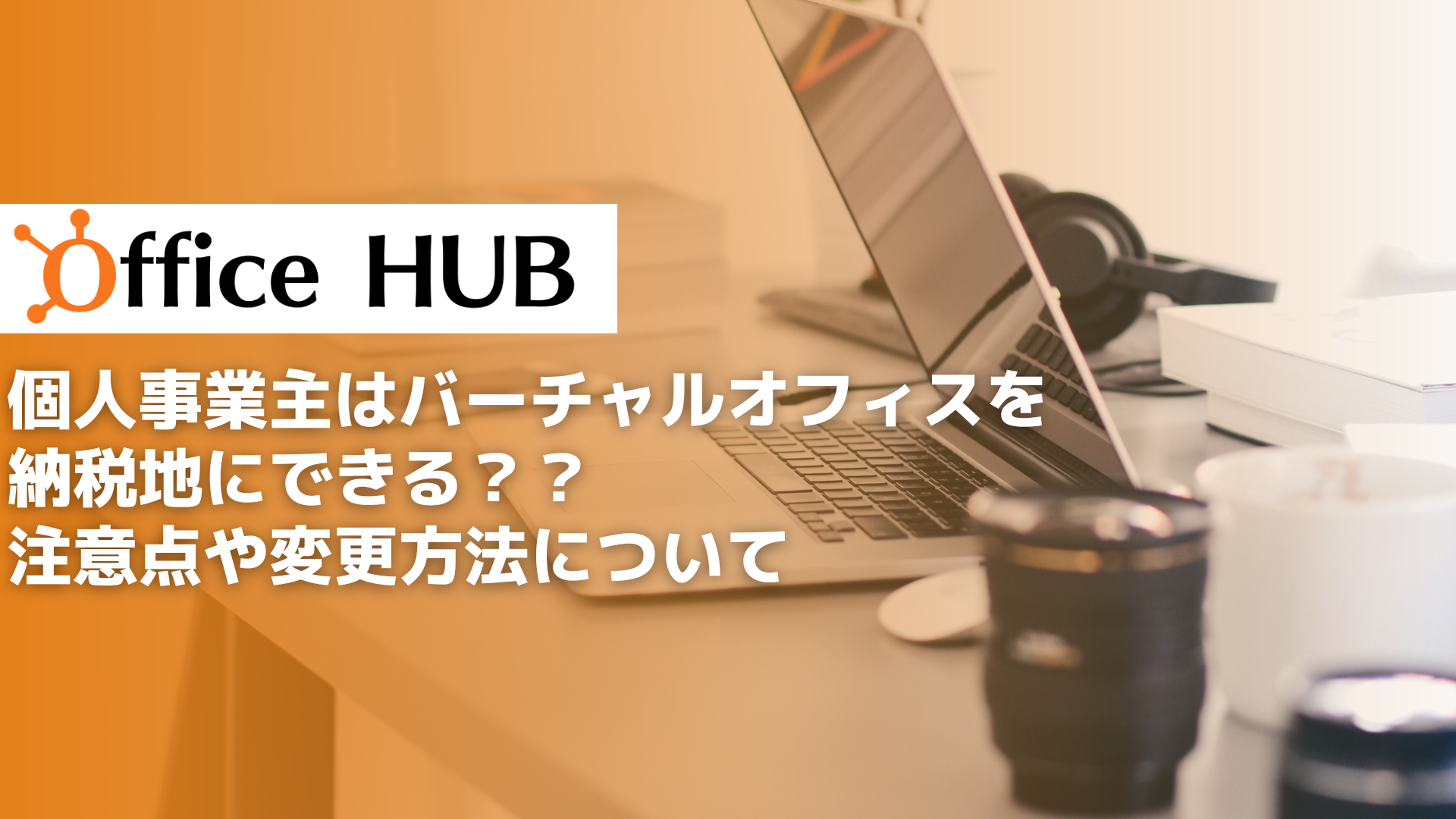

コメント